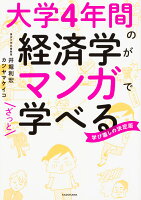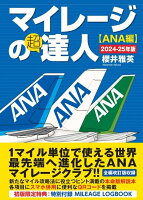家庭菜園のきゅうりが...
私が住むエリアは基本的には住宅地という色彩が強く、
一部、昔からの小規模工場だったり、
オフィスだったりがあります。
なので、農地的なものは一切ありません。
そんなエリアにある普通の住宅の前に、
段ボール箱に入ったきゅうりが3本ほど入っていて、
「ご自由にお取りください」
と書いてありました。
どうやら、鉢植えで作ったきゅうりらしく、
取れ過ぎたからなのか、
欲しい人はお好きにどうぞということらしいです。
都内でそのような光景を見るのは初めてなので、
ちょっとびっくり致しました。
無料なら貰おうかと思ったが...
きれいな形のきゅうりでもあったので、
無料なら貰おうかと思ったのですが、
やはり知らない方から貰うのは抵抗がちょいとありましたね。
しかも食べ物なので、
万が一何かあるとちょっと嫌だな~とも思いました。
それにしても、食べきれないほどきゅうりを作るのはなぜか?
余ったのなら近所に分けるとかしないのか?
色々と疑問に思いましたね。
食器くらいなら貰うかも?
まあ、今回は無料のきゅうりはスルーしましたが、
特別高いものでもないので、
欲しければ買うということで良いでしょう。
そういえば最近ですが、
いらなくなった食器らしいものを、
ご自由にお取りください!
と家の前に並べている人が多いです。
食器くらいなら良いのがあれば貰うかもですが、
なかなか丁度良いものがないのが実態ですね。
そりゃ~、そんな良いものはタダでは配らないといったところでしょう。
にほんブログ村