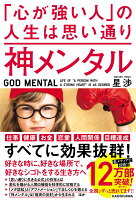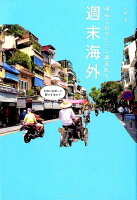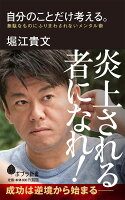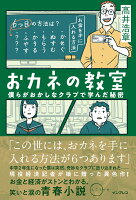50代前半に落ち込みの谷が最も深い
50代になると仕事に積極的な意義を見出せない...
確かにその通り!と唸る記事を読ませて頂きました。
"『ほんとうの定年後』のなかでも反響の大きいのは、50代の就労観に言及している部分である。〈多くの人が仕事に対する希望に満ち溢れていた20代から、人は徐々に仕事に対して積極的に意義を見出さなくなっていく。そして、落ち込みの谷が最も深いのが50代前半である。この年齢になるとこれまで価値の源泉であった「高い収入や栄誉」の因子得点もマイナスとなり、自分がなぜいまの仕事をしているのか、その価値を見失ってしまう。定年が迫り、役職定年を迎える頃、これからの職業人生において何を目標にしていけばいいのか迷う経験をする人は少なくない。そうした現実がデータからうかがえるのである。〉(『ほんとうの定年後』より)” (引用元) 退職金も激減、転職しても給料減…50~60代で「仕事の意味がわからなくなる」人が続出"
特に、50代前半に落ち込みの谷が最も深いというのは、
私の感覚ともマッチしますね。
40代半ば以降の仕事は不発
私の場合を振り返りますと、
既に40代半ば以降に私がやっていた仕事は、
基本的に若手でもできるような仕事がほとんどでした。
なので、仕事の意義など既にゼロになっていました。
結果的に私は50歳で仕事を辞めることができて事なきを得ましたが、
50代以降も働いていたらどうなっていたか?
恐らく上司は10歳くらい年下の人がやってきて、
仕事は単純作業的なものの比率がアップ、
役職手当がカットされるなど減給になっていた確率が高いです。
となると、仕事の意義などはマイナスに転じていたでしょう。
セミリタイアとかFIREという概念を私が知らなかったらと思うとぞっとしますね。
転職した場合の懸念
記事では、転職というアクションをとっても、
50代の転職は賃金が減るということを述べています。
ただ、50代の転職など難易度が極めて高く、
賃金云々以前に同じ職種で転職できるのか疑問な点があります。
また、実際に転職できた場合の私の懸念はちょっと別のところにあります。
というのも、比較的私の仕事に近い職種の同年代の人が、
会社の待遇に不満を覚えて転職したケースがありました。
待遇面はアップしたそうですが、
転職先は超激務だったそうです。
私の考えでは、それなりにやりがいのある仕事だっとしても、
50代以降の体力では超激務は勘弁して頂きたいところです。
この辺は転職時の条件で隠される可能性が高く、
これに上司ガチャ的な要素も加わるとなると、
50代の転職など怖くてできたものではないな~と思った記憶があります。
そういった外部要因に振り回されないFIRE生活を、
50代で選択できたのは結果論的にも大ラッキーだったというのを、
記事を読んで改めて感じた次第です。